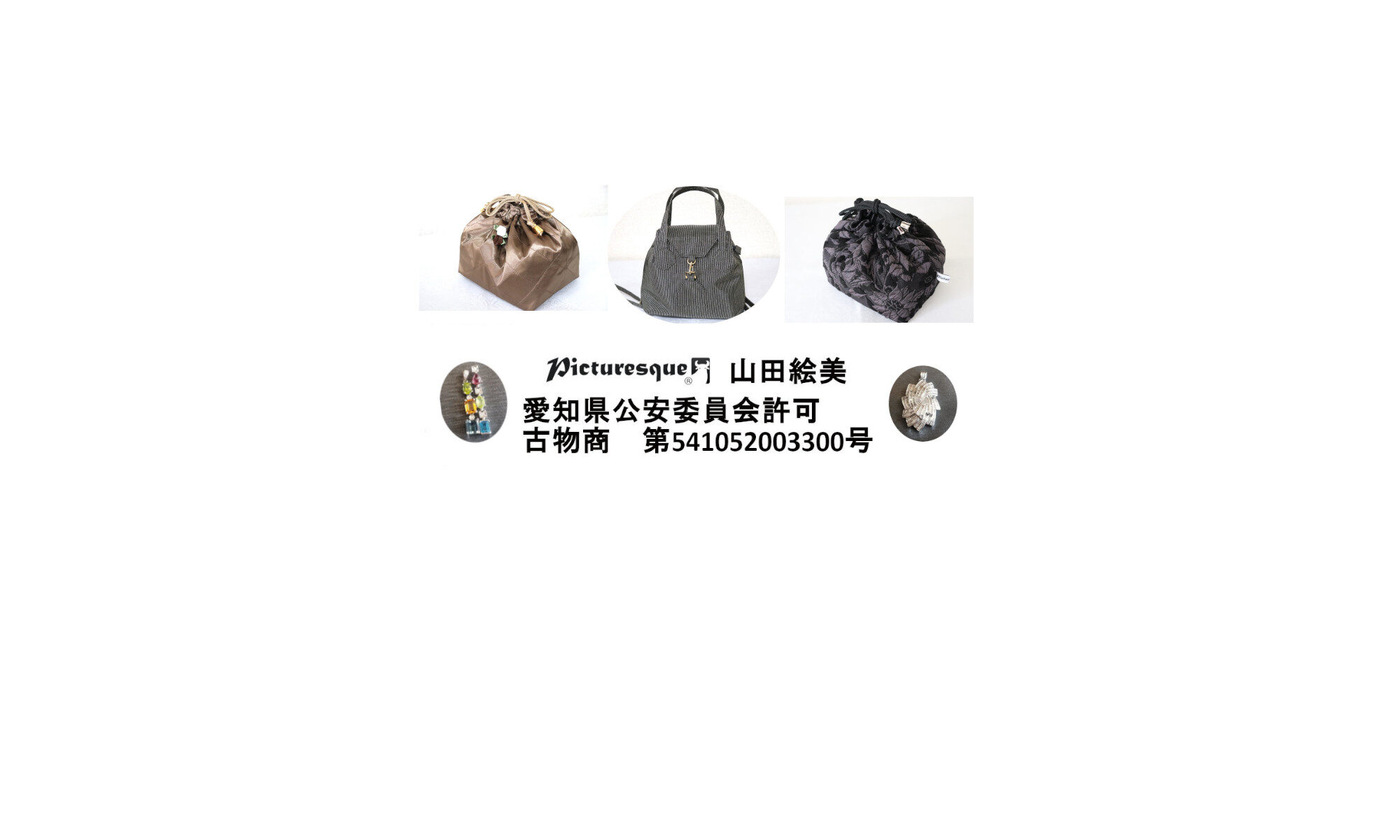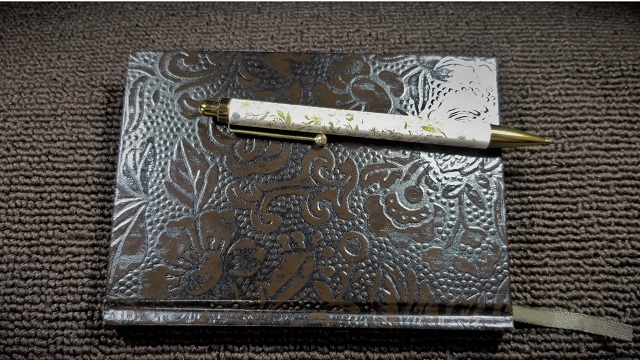まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
個人事業主をスタートさせて、現在ちょうど3ケ月が過ぎたところです。
日々、初の売上を作ろうと懸命な「ハンドメイドバッグ製作+マーケットサイトで販売」の最初の3ケ月の中で並行しながら、「経理事務」のお仕事があります。
会社員時代には長年「経理事務」に携わっていましたので基本的には心配するところはありません。
しかし、実際は、「マネーフォワードクラウド」という「(株)マネーフォワード」様にお世話になっている会計ソフトに、日々の取引を計上していく中で、「これでいいのかな?」など、モヤモヤして、はっきり分からないことなどが数点出てきておりました。
「マネーフォワードクラウド」にも質問はできるのですが、あくまでソフトの使い方などに範囲の限界があります。
のぞましい仕訳や、特殊なケースへの計上する手前の事項に関しては「税務署」様に聞くべきなのです。
そんな頃に、タイミングよく税務署様から、帳簿の記帳説明会のご案内を郵送でいただいたので、「よし、参加して質問してすっきりしてこよう」と思ったのです。
そして、先日4月中旬あたりでしたが、参加してまいりました。
このたびは、実際に参加した「税務署」様主催の「帳簿の記帳説明会」のルポタージュとしまして初めて事業主になられた方のためになるところがあればと、その時の実直な内容をお届けしたいと思います。
「帳簿の記帳説明会」のおおかたの流れ
ネットで、事前に記帳説明会に行った感想のようなブログ記事(このたび私が綴っているようなもの)を数件読ませていただきました。
感想は人によってさまざまでしたが、なかなかインパクトのある感想は見つからなかったです。
あまり、感動的な良かったという感想も見当たらなかったです。
やはり、実際に自分で出向いてみるのが一番だと思いましたし、質問をしたい内容が解決できるなら、行く意味は必ずあるだろうということで出かけていきました。
事前申し込みは必要なく、当日そのまま会場へ足を運べばよいというのが、とても行きやすかったです。
部屋の椅子の数の50人前後の定員がある程度決められているようでしたが、実際は、10人いなかったと思います(驚)。
税務署様がご用意の資料を「パワーポイント」を使ってお姉さん(税務署員様)が説明して下さいました。
記帳説明会の時間は、1時間半程度でしたね。
さて、参加して良かったのかどうかですが、迷うことなく、「良かった」です。
反対に、参加しなかったらと想像すると寒くなるほどの大きなイベントだったと思えます。
この後に綴りますいくつかの学びがあることでこの「良かった」「意味があった」という感想がいかにリアルなものであるかを感じ取っていただければと思います。
参加して良かったと改めて思う、初の情報の数々や大鉄則事項
1)クレジットカードと預金の残高ともども、月末では「帳簿」と「実際」の完全一致の鉄則
記帳説明会の参加を終えて、これは重要なポイントだと感じたことがあります。
説明会に参加する前は、実際にできていなかったことでもありました。
とにかく、預金通帳の残高と、帳簿の残高が一致しなければならないとうことが大鉄則とのこと。
クレジットカードも同じように一致しなければなりませんが、クレジットカードの引落も普通預金からなので、当然、連動して一致が余儀なく求められます。
よく、個人事業主になったら、「専用のクレジットカードを作るべき」「普通預金の口座も専用に作った方がよい」などは、ネットでも拝見したことがあった情報です。
専用のカードや口座を作ることは、多少分かりやすいですが、それが必ずしも重要ではなくて、むしろ「残高を一致させること」の方が重要なのです。
自身の場合、特に今までの個人のままの延長でクレジットも普通預金も継続したかったので、新規には一切作りませんでした。
結論から言うと、これでも「全然大丈夫」です。
ただ、預金の中に、個人(事業外費用)の使用の内容の物も含まれ、クレジットカードの内容にも、個人(事業外費用)の内容も混じるわけです。
それをクレジットカードの引き落とし日に、まとめて1本の計上をする必要があるというのが初耳。
自身は除外して、計上せずにいまして、「残高が合わないのはそういった事情で仕方がないと認められる」というような勝手な解釈をしていたのです。
それで、普通預金の月末の残高や、クレジットの月別合計が、ぴったりにならない状態で2-3か月を過ごしていたのでした。
絶対的なものでないから、仕方ないと認めてもらえると思っていたというところが大きな勘違いだったのです。
ほら、こういうことがあるから、こうした説明会でご質問する意味が大いにあるのです。
「法人」と同じで、完全一致であることが絶対だとお話を聞き、「頑張って合わせてみてね」、と税務署のお姉さんに言われ残高を合わせる作業を2-3日にわたって行い、やっと一致に至りました。
そこで、完全一致のために使う重要な勘定科目が、
・事業主貸
・事業主借
という2つの科目で、例えば、自身のような個人用と事業用が混在しているクレジットでも、
事業主貸 50,000 普通預金 50,000
「〇〇月分事業外費用(総合計) 支払 △△カード:xx銀行」と摘要欄に入力。
こんなふうにたくさんの合計を1行にまとめて事業外費用一括として、シンプルな計上で全然良いと、税務署様がおっしゃっていました。
この後に、「総勘定元帳:普通預金」で残高を「帳簿」と「通帳」で合致する確認をするのです。
クレジットは、事業専用に作るのも確かに良いです。
ただ、他の明細がどうしても混在するケースがどこかで必ず出てくるので、綺麗に分かれるということが難しいです。
例えば、事業用と個人用とで50%ずつの使用としています「地代家賃」という科目の場合、事業用のクレカを作っての支払いをしたところで、結局は、家賃を事業用と個人用に分ける2段の計上をせねばならないです。
さらに、家賃が実際に引き落ちるカードが事業専用の方ならば、結局は個人用の家賃の部分の金額も一緒に引き落ちる運命ではありませんか。
よって、クレジットカードは個人使いの1つのクレジットカードを事業用と共有し、中身の内容だけをクリアに分けることでかえって、1本のクレカの管理だけでに集中できるのだと考えるとむしろこの方が良いというのが自身の考え方です。
2)「預金利息」の入金は「事業外収入に該当」という決まりがある
「預金利息」で一番共通するのが、「普通預金利息」です。
普通預金に、「預金利息」がほんのわずかの金額ですが入金された場合など、これは、「事業のものではない」という決まりらしいので、いくら、事業主用に専用の口座を設けていても、
普通預金200 受取利息200 ・・・ x
という仕訳はダメで、
普通預金200 事業主借 200 ・・・ 〇
が正解。
ここでも結局、個人が混在してきてしまうのです。
3)「現金」のマイナスの残高は認められない(現実的な矛盾)
もう1つ、現金の残高はマイナスは不可というのも大鉄則とのことです。
マイナスになっているということは、計上などにミスがない限り、個人のお金から事業に使っていることになりまして、その流れを都度リアルタイムで計上します。
現金 100,000 事業主借 100,000
※振替(個人用現金⇒事業用に)
これで、個人の私のお金を事業へ投入したということになります。
会社であれば、会社専用に現金がはっきり分かれていますから、現金ボックスなどの現物を数えて、総勘定元帳の現金の残だと一致しているかを調べるということになります。
一方、個人事業主の場合は、たとえ事業用にボックスを作ったとしても、何か購入する時は個人の財布からということが多いですから、現金を別に分けておくということはなかなか困難です。
そこで、時おり、現金の帳簿をチェックすることを心掛けるといいです。
自身は、毎回現金の出費の計上をした後に、必ず帳簿上の「現金」の残高とお財布の現金を数えて合致を確認しています。
それならば、お財布を「個人用」と「事業用」に分けて管理はどうかというアイデアが浮かぶかもしれません。
実は3年程お財布を分けてやってきた結果が出ています↓。
あまりに管理がしにくく、その後はずっと1つの財布だけで管理になりました。
お財布を2個もバッグに入れてとても野暮ったいですし、結果は混乱の原因になるだけでした。
その代わり、ちょっとしたお菓子を現金で購入しても会計ソフトに、
100 事業主貸 現金 100
※お菓子1個(事業外費用)
を入力することになるのです。
とはいえ、それでも自身はこちらの方を選択したのでした。
4)簿記の教科書に登場の、「仕掛品」「製品」は通常の計上では省略してシンプルに
ここからは、前もって準備していた質問に対して税務署様からいただいた回答をご紹介したいと思います。
どなたかのネット上のブログで、自作商品を製作している人の仕訳ということで、工業簿記を引用してみえました。
①材料仕入 現金(材料購入時)
②仕掛品 材料仕入(作業に取り掛かった時)
③製品 仕掛品(商品完成時)
④売上原価 製品(商品が売れた時)
と作業の順に振り替えていくのだということが書いてあったのを拝見しました。
これは確かに、工業簿記に従っています。
しかし、とても複雑であり、頭が痛いです。
税務署様によると、「商業簿記風で簡素で良い」とのことです。
①材料仕入 現金(材料購入時)・・・②③④の仕訳は無し。
⑤売掛金 売上(商品が売れて受け渡し時)
これだけで良いのです。
「受け渡し時」は、商品を発送した日でも、相手が受け取った日でもそれは、ご自身の方針通りでどちらでもいいとのことです。
そして、実際に入金があった時に、
⑥普通預金 売掛金(商品代入金時)
を仕訳します。
ということで、①⑤⑥だけの仕訳しか現在も使っておりません。
「製品」という科目は、通常は使いませんが、決算仕訳の時だけ「棚卸仕訳」の計上の際に使うことになります。
5)「保険料」の支払いの計上はすべて「個人扱い」であり事業の費用とはみなされないルール
・国民健康保険料
・国民年金保険料
これらは、「確定申告」時には控除対象になるもので、申告はしますが、その都度の計上は、
・国民健康保険料・・・事業主貸 - 普通預金(自動引落日だけ計上)
・国民年金保険料・・・事業主貸 - 普通預金(カード引落日だけ計上)
で「事業主貸」の科目を使って計上しなければいけません。
税金関係は個人のものだから、「保険料」という費用の科目を使用してはいけないのです。
※ちなみに、「住民税」というのがありますが、これがよく分からず、住民税支払い時に一度税務署様に聞いてみました。
「仕訳もなし、確定申告もしない」これが正解です。
6)不用品の販売と収入(「ヤフオク」や「メルカリ」で衣類や雑貨を販売した場合)
このこともよくある話題なのですが、実際に税務署様にお聞きしました。
前に買ったたくさんのお洋服などが不要で、現在ヤフオクで売っています。
それでも、個人の持ち物である衣類などの不用品販売というのは、売上の多少、関係なく「申告対象外」とのこと、計上も無しでよいそうです。
一方、「せどり」「転売」など、事業として行い、個人の不用品販売とは明らかに違う場合は、「事業要素が高い」と判断されますので、「計上も申告も必要」とのことです。
事業者としてそういった「せどり」「転売」をしているかどうかなどは、ご本人が一番分かっていることです。
正直なのが後々楽なのです。
あとがき
今回、初めて経理部門のカテゴリーの記事を書いてみました。
もしかして「自身の経理経験が生かされた部分があれば」ということ、ネットで調べてもなかなか完全な答えが見つからなかったこと、がこの度お伝えしたことの中に入っていれば幸いでございます。
「普通預金口座の一致」や、「現金がマイナスになるのは不可の鉄則」は、かえって、計上もれや、重複の答え合わせにもなる良い鉄則なのです。
自身もまだ個人事業主経験が浅いですので、まだ多くのことはお伝えできませんが、今後、この<事業><経理>のカテゴリーにも、経験が増えてきたら、記事を増やしてお役に立ってまいりたいと思います。
お互い、事業の発展と実りを目指しながら日々の事業活動を頑張ってまいりましょうね(^-^)。