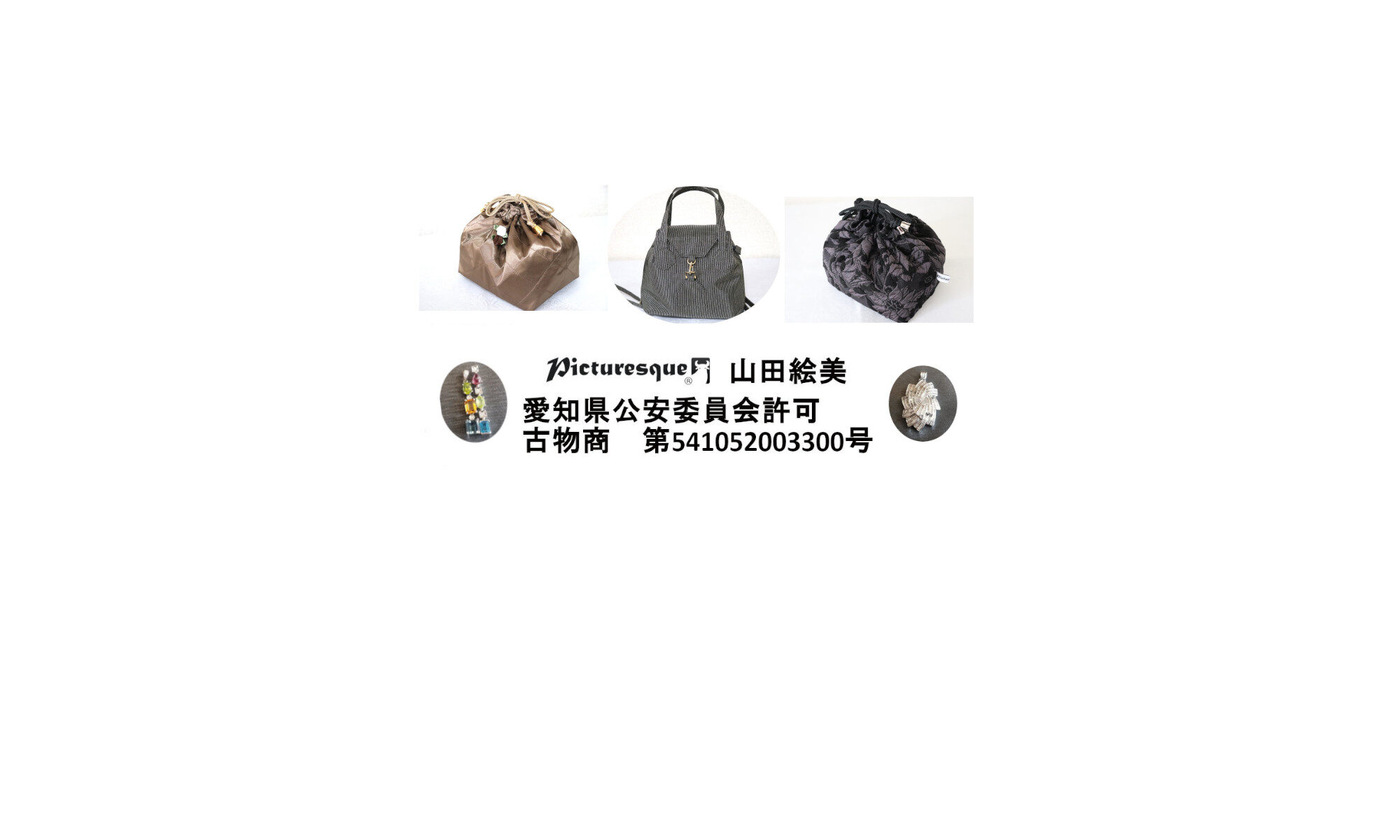まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
昨年の12月の途中から5点同時に製作してきたハンドメイドバッグ、ついにこのたび最後の1点が完成しました。
デザインは「かまぼこ」というボストン型の小さめサイズです。
最も生地が多くあった抽象柄のピンクxグリーンのジャガード生地(イタリア製)での製作です。
ここまで作ってきてもまだデザイン変更の必要性を感じた果てしなく続くバッグ作りのストーリー
ところで、前回の【330】の記事でアップ致しました内容の中で、底のカーブをきちんと重ねることの対策として、仕付け糸を細かくするというものがありました。

先回の時点では、もっと徹底してきちんと本体と口布を重ねていくということでいったんまとめたのですが、その後考えが変わりました。
この部分は、この時点だけでなくそれ以前のひっくり返しの時もこの細かい角を正確に出さねば、最終的にぴったり合わないのです。
よって、難易度が高い場所になっています。
要するに成功する確率は低めなのです。
そもそも成功しにくいデザインを見直すべきではないのかということ。
そこで、こういった結論に達しています。
カーブが急であることが原因、デザインを緩やかなカーブに変えよう、と。
カーブが上手く重なったケースのゆるやかな角度の時と同じデザインにするのです。
そうしてデザインの大幅な変更を決め、全体の印象を大きく変えていくのです。
ただ、サイドのラインがストレートなままであると別の定番商品の「テリーヌ」と全く同じ形になってしまいます。

サイズは違えど、スクエアな四隅が均等のイメージになるので、テリーヌに近づくのです。
ということで、サイドのラインがまっすぐ降りていたのを斜めに変更していくことで差別化をはかります。

この写真を見ていただくと上の両端の緩やかなカーブから下まではストレートのラインで降りています。
元の型紙もまっすぐストレートに作ってあります。
これを外に開くようなカーブにして、上と同じ角度の円の一部分の時点になったところでつながるという型紙に変えてみます。
早速修正してまた、製作してアップしてまいります。
同時製作の結果分かった複数同時製作の効果が大きく出る条件

複数同時製作の効率のことを見てみたくて、同じ素材、同じデザインをミックスした5点にしてみました。
この結果からの感想をお伝えしたいと思います。
そもそも、取っ手と取っ手の付け根タブ、ショルダーに関しては、「おにぎり」、「かまばこ」、「餅巾着」の3デザインすべてに共通にしてあります。
このことがかなり良い方向に影響しました。
最初の方の裁断の段階であまり進捗度は良くなかったですが、その後地道に共通のパーツをどっさり次々に作っていって取り付けていきました。
縫製の段階では、デザインが違っても同時進行できたことが作業がスムーズにできることに少なからず好影響を与え、そもそものデザインの共通部分ということにメリットがあると感じました。
では、かまぼこの3点は素材が全く違う3点で、糸の色をその都度変える必要がありましたことに関してはどう感じたのかです。
この糸の色を変えることは、同時製作にすごく不利ということは特に感じませんでした。
糸を交換するのはものの数十秒、デザインが違うということに比べると糸交換の手間は軽かったです。
まとめると、とにかく同じデザインを同時に製作するという条件は、生地の種類や色が違って糸交換が出てきたとしても、効率アップの効果があったと感じたというのが正直な感想でした。
あとがき
デザインを確定し、「これだ」とその時は思っても、その後少しずつの改善が出てくるものです。
むしろ、デザインを決めたからこそ見えてきたことなのかもしれません。
変化しなければ、発展はないという言葉が浮かびました。
もどかしいことですが、「これでずっと行くのだ」というデザインなど無いのかもしれません。
改善に改善を重ねて、もっともっと良い物に変わっていくことのその途中の試行錯誤こそが長い目で見た未来の品物に「詰め込まれる」ということなのかもしれません。