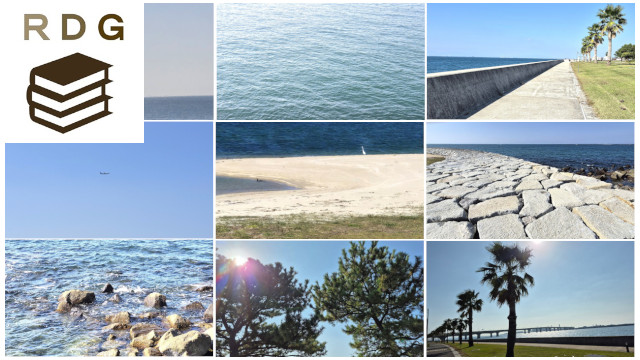まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
このたび、「生き方:稲盛和夫 著」を拝読。
以前の「稲盛和夫の実学 経営と会計:稲盛和夫 著」について【1435】で投稿させていただきました同じ著者様の本です。
口コミでも随分多く広まった本。。図書館で借りたものですが本の傷み具合からもよく分かりました。
このたびは、後で貼りますYouTube内の3項目以外の「因果応報:いんがおうほう」について綴りたいと思います。
この言葉は、「悪行はいずれつけのようなものの巻き返しに代わる」というような、悪い方の報いとして語られることが多いですが、実は善行の方の側面もあるのです。
「因果応報」をまさに受けているのではないかという誰かの姿が見えた時、他人事ではないと「慈悲」の目で静かに戒めとして見届けたいものです。
間違っても決して「当然だ」「今までの行動の報いだ」などと揶揄してはいけない、自分自身への戒めでもあるかもしれないと思うべきです。
商人の望ましい有り方が綴られていた。。「我欲」と対極の「利他」を持つことができることは発展や平和につながるもの

著者様は、後に「仏門」へ入られていました。
仏教が教えてくれる大切な言葉を腑に落とし、ビジネス分野にとどまらない人間の望ましい有り方を教えていただいた本なのです。
「長い目で見る」という言葉が好きであることを過去のブログ記事でも時々お伝えしてまいりました。
「因果応報」は、良い方も悪い方も実に長期スパンで起こることのようなのです。
よって、短期的な姿勢で答えばかりを常に追い求める行動では、探索に大半の時間を費やすので、かえって時間が足りなさ過ぎると言えるのではないかと。
長い時間をかけて実らせる「覚悟」は、そもそも持っていないといけないな。。と思っています。
商業というのは「利」を追求するものであるのに、近い意味の「我欲」だらけでは立ち行かない点が混乱と勘違いを起こしているかもしれません。
本の中でも何度も使われていた「利他的」は、肝に銘じておきたい大切な言葉でした。
そう考えると、「利益」が必ずしも事業者のみのものではないと言えます。
利益からの「寄付」などは、その理解しやすい一例なのではないでしょうか。
「利益」は皆の物、従業員や家族や寄付先に分配されることの意味が奥深いのです。
あとがき
こういうアウトプットは、耳が痛過ぎてあまり多くの方には見てもらえない内容みたいです(^_^;)。
それは、多くの方々が「我」に傾向している証ともとれます。
気持ちが良い程の透明感のあるこの本、とてもじゃないけど目を背けたい程の方もいらっしゃると思うのです。
ただ、これまで多くの方々が手にされた本なのですから、著者様の考え方に倣う一員になりたいですし増えると良いです。
こうしたことの「模倣」なら本当に良い意味での真似だと思うのです。
見かけのフレーズのカッコ良さやちょっとした小手先のテクを気軽に模倣する傾向が多いのは、まさに短期的なゴールを目指す行動。
あちこちそのような大変な調査をしなければならないのも、「軸」が無いからです。
それでも、そのような方に対しては「因果応報」を当てはめてその先の悪い未来を予想して蔑むことは控えねばなりません。
「軸」が無いことの苦しさはそれもそれで相当なものであり、自分なりの「哲学」を持って歩んでいけることを僅かばかりでも願ってあげなければいけないと思い直しました。
真似されて悔しい思いをされている方も多いと思いますが、たやすく模倣をする側も苦しい思いをしていることを、少しばかりの慈悲を持ってわずかながらも理解することです。
自分が足りなかった部分はこの部分、本の内容からはやや逸れましたが、悪い「因果応報」など誰にも本当は起こらない方が良いと思う気持ちを持っていきたいと思ったところです。