まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
このたび拝読したのは、「風土:和辻哲郎 著」。
紹介されていたのは、新聞だったと思います。
私くらいの世代で「戦争」とイメージするのは、第二次世界大戦の1940年代。
この本は、それ以前の1928-1929くらいからまとめられ1935年に出版された、「戦前」と呼ばれる時期に生まれた本です。
今この古い本が意味するところは非常に大きく、過去の民俗学の専門家がいかにも大切なメッセージとしてその後の未来への懸念や警告をしてくれたようにも受け取れるほどの内容。
現在の「移民問題」に大いに通じる内容だからです。
気候や環境によって国民性は根を張りながらしっかりと作られてきた、まずは自国の特殊な部分をよく知ることから。。
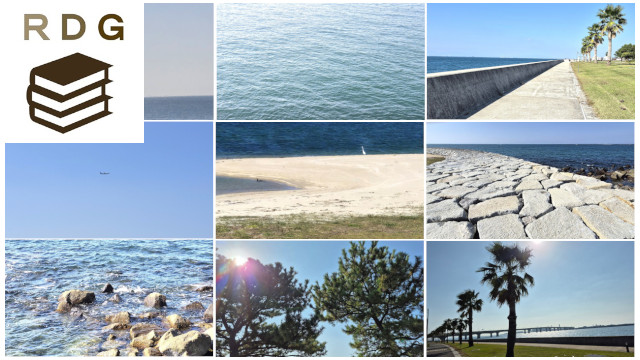
多くの外国人が訪れる日本、現在の物価高背景の中での円安傾向の旅行は非常に分かり易い人々の動き。
ただ、もっと長期的な問題は人口減少であり、自国民だけでは事業者・消費者共に不足の事態で商業が成り立たなくなるということが考えられます。
外国人の労働者の手を借りながらでなければ本当にどうしようもないものなのでしょうか。
少ない人数でも成り立っていく手は本当に無いのでしょうか。
「最後の民族」というような貴重な存在は、長い長い年月の経過と共に消滅してきたことが、ある地方の古い民族の最後の人のインタビューで見ることがありました。
その表情は切なく、その土地の文化や精神を受け継いできた誇りも同時に感じたものです。
この本の中にも取り上げられていた「モンスーン」の気候の特色を持つ日本、特に台風の多さの特徴などからもアジア地域の中でも独自性を持ったものであるようです。
一方で、砂漠の地の人々の国民性、ヨーロッパの人々の国民性と異色のその他2地域を主に取り上げて比較されています。
芸術面でも、数学的配列や規則性を重んじる絵画や彫刻にその土地のヨーロッパのシンメトリーな考え方が表れます。
一方で、左右非対称でありながらも全体としての調和が出来上がった「盆栽」という芸術品の世界観は日本の独自性の表れという見方。
列を作ることが周りとの調和を重んじる日本らしい精神として映る一方、イギリスの「パブ」では、列になど並ばないことこそ文化であり、カウンターに腰かけたお客様の順番を店主の裁量で順番に平等に捌く文化があるとのこと。
必ずしも列を作り並ぶことが絶対的で世界的ではないということの1つの例です。
この本の中にあった一番印象的な部分はここ↓。
「風土がそれぞれ別物で分かれて区分されていることこそ、それぞれの特性が平和な形で活きる」という考え方です。
なるほど、混ざり合わないことこそがかえって「バランス・調和」なのだということには非常に納得しています。
あとがき
ある一定期間の海外旅行と住みつくということは「全くの別物」という程の大きな違いがあると思います。
家をかまえて住むところまでの状態は、ある意味「覚悟」のようなもの。
本当に自分が生まれ育って根付いた考え方や精神を持ったまま、他の考え方や精神に本当に馴染み切ることができるのかということ1つ。
そして、もう1つはそこにあった良き文化や精神が消滅してしまう懸念です。
「おじゃまします」「失礼します」「良き塩梅」「それとなく」。。日本語のワードの中にある良くも悪くも日本人らしさ。。決して失いたくないですね。

