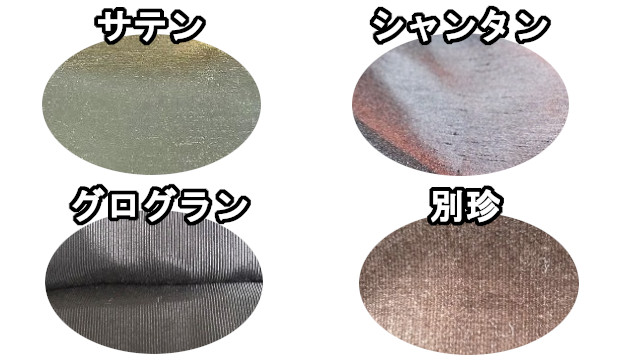まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
このたび、一気に4冊連続で、産地品である生地についての本を拝読。
1)「糸がつむぐお話 一宮のまちと繊維産業:末松グニエ 文(あや) 著」
2)「糸がつむぐお話Ⅱ~尾州ツイード~:末松グニエ 文(あや) 著」
3)「大島紬誕生秘史:重村斗志乃利 著」
4)「ヨーロッパのテキスタイル史:辻ますみ 著」
1)の地域に3)の地域の方が視察に訪れるような場面もあり、生地発祥の当初はそんな風につながりもあったのだということが驚きでした。
このたびは、得に1)2)については住んでいる地域の近隣であり、これまで繊維分野にたくさん触れてきたことで今後のアイデアみたいなものを考えてみました。
世界からも注目されているハイブランド様御用達の傾向もある「尾州ウール」に関して、3)の大島紬に関して、4)の海外の生地に関してをそれぞれ、自らの言葉で、今思うことをまとめたいと思います。
「尾州ウール」の可能性・・・1)2)
どうしても、お洋服で言うと「冬」をイメージしがちなウール。
重いイメージから季節が限定され、実際にも重衣料に向くような素材ではあると思います。
しかし、受け取る私達も、変なイメージをいったん取っ払い、もっと取り入れ方を広げるということが今後の存続と広がる可能性を生むのではないかと考えます。
黒生地だとウール100%だったとしてもバッグには違和感もないですし、以前にウール100%でバッグもを作ったことがありますがとても使いやすかったです。
ウールは保管すると虫が好み穴が開いたりすることが多いので、常に使うものに取り入れるのも1つの手ではないかと思います。
「季節感」も時として使用時期の縛りをもたらしてしまうので、使用機会が減ってしまうとも考えられます。
今後は、お洋服で数が多い綿/100%、ポリエステル/100%など共に毛/100%であってもフラットに見る目というものが受け取る我々にも大いにあることが望ましいかと。
「大島紬」の美しい柄を出すための「絣筵:かすりむしろ」の手間のかかり具合・・・3)
通常の織物との違いが「大島紬」にはあり、手間がかけられた芸術的な素材。
「締め機:しめばた」という機械に糸を交差させてその後の「染め」作業後美しく柄が出るための「絣筵:かすりむしろ」を作るそう。
この本の読みやすい点は、解説形式をうまく物語と溶け合わせた綴り方である点。
ノウハウ的な硬い説明のみだとなかなか新しい知識として浸透してこないのですが、当時にタイムスリップしたかのように昔話になっているところが忘れられない1冊となりました。
この本の中で熱心に「図案」を考える姿がありました。
やはり、必ず柄はどこかの誰かが考えたもの、「著作権としては無し、もしくはグレーゾーン」の着物の柄とも言われているようですがこうして一読すると、いやはや芸術品のようだと思えてくるのも確か。
「シノワズリ」という呼び名は、貴族の時代のヨーロッパから見た「中国」の芸術品のテイストのこと
17世紀中頃から貴族の間で、他国のテイストを楽しむ文化が栄えた中に、「中国風」のテイストが「シノワズリ」という名前で呼ばれていたそう。
これも模倣の1つで、フランスの独自の解釈によるもの、山などの風景画やボタニカルな花柄などの陶磁器へと製造された文化があったのでした。
他国のテイストはあこがれるもので、我々がヨーロッパのテイストにあこがれるように、互いに新しい感覚に対して興味があり惹かれるのです。
ただ、あくまで呼び名であり、その定義は曖昧ですが、日本の伝統的和柄も元は中国から伝わったところから始まっていまして、中国は他国に多大な影響を与えていたのだと思います。
いかにもヨーロッパ生まれと思えるような柄も、実は中国のテイストの模倣や引用によって取り入れられたきたこともあること、日本にも伝わった中国生まれの柄などの事を考えますと、中国の影響力は多大です。
あとがき
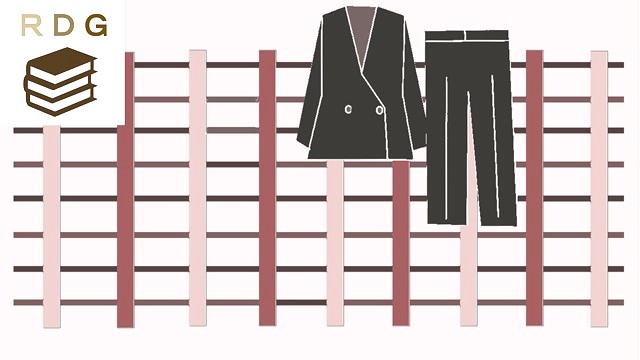
古い本であっても、産地の素材の本は不変の内容であることで一読の価値もあるものも多いです。
ただ、読みやすさなどは近年の活字離れへの工夫として読みやすくなっているところも感じます。
品物を製造するには必ず材料が必要。
すべての始まりは材料の選択にあり、生地のバッグを作るのだと特化していてもその中でどの生地なのかという特化においては、このたびの4冊連続の拝読がとても参考になりました。
3)の大島紬だってバッグにすることができるのです。
ただ、着物として作られたものを解体するのか解体などしないそのままの姿こそが良いのか、はたまたお洋服にした方が柄が広いままで使えるのかなど考えるところは多数。
「リメイク」もむやみに解体して作業する前に、こうした元の背景も一度考えた上での判断が良いと思います。
実際に着物を購入したものの、あまりに美しくて、解体できずにリメイクを躊躇している方のお話をうかがったことがあります。
それは、素晴らしい柄で作られた品物に手を加えることへの躊躇だと思います。
「伝統を守る」とか「産業の継続」ということがどういうことなのかを製造者側だけでは足りなく、受け取る側も同時に考えてみるきっかけはこういった本の良さだと思います。
一読後こうしてアウトプットすることでどなたかに記事を読んでいただいて何を感じたのか、どんな意見を持ったのかというように連鎖してゆけばよいと思いました。
どうぞ、このたびの記事を一読いただいた後に、どんなことを思ったのかというところに注視してみてくださいませ(^-^)。