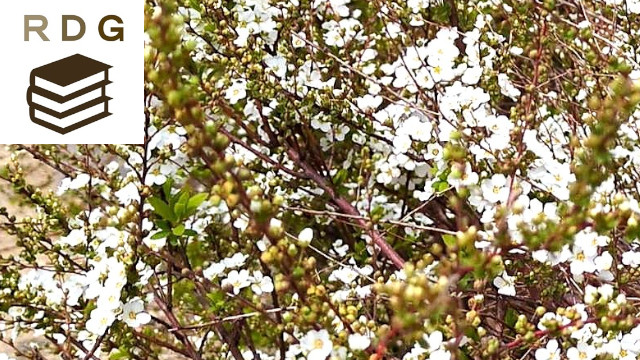まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
2018年にスタートしました、当「ワードプレス」様を利用させていただいております当ブログ記事でもこれまで随分ファッション分野に関して投稿させていただきました。
10個のカテゴリーの中では、<コーデ>がアパレル分野の所謂「ファッション」という分野の内容に合致するものです。
その中で、「ヴィンテージ」というワードを時々使わせていただいていたのです。
この「ヴィンテージワンピース」などというように。。
ブログ記事を投稿するにあたっては可能な限りを尽くして、「正確さ」は意識しておりますので、ちゃんと調べて30年もののワンピース(今からは1980年代-1990年代初めくらいのもの)などを自己確認のもと「ヴィンテージ」と綴っていたのでした。
ところが、ここ最近の世界的ファッションアイコンなる方(私もとても尊敬する方)が、インタビューの時に、「ここ近年は、かつての素敵な古いお洋服が見つからないから残念だ」というような内容を発信されたようなのです。
そのことがすぐにライター様により記事になり、みんなが見るようなネット上の公開記事として掲載。
注目は、この記事に対するコメントでした。
「20-30年やそこらではヴィンテージと呼ばない、せいぜい50年前以前でなければ。。」というコメントが軒を連ねていました。
本当に、偶然に発見した記事でしたが大いに関係ある話題であり、是非ここでピクチャレスクとしても、この「ヴィンテージ」というワードに関して綴りたいと思いました。
古着のブランディング化、「ヴィンテージは何年から?」は、かつては確か30年と聞いていたのに、現在は50から70年前でなければならないようだ

インタビューを受けた方は、決してヴィンテージの定義を語ったのではありません。
「ここ最近良き古きお洋服が古着市場で見つけられない」という古き良き味わい深いお洋服が減ったという嘆く内容をおっしゃっただけなのです。
しかし、コメントは、「ヴィンテージが何年からなのか」という切り口に替わっているところが不思議でした。
このことが何を表しているのかが、ピクチャレスクなりに理解できましたので、紐解いてみたいと思います↓。
まずアンティークの定義は「100年以前」としっかり線が決まっていますが、ヴィンテージは「100年未満」とだけで、範囲が曖昧なのです。
様々な解釈の仕方が溢れるのも仕方が無いのです。
確かに2018年辺りにブログを投稿するにあたって調べた時には、「ヴィンテージは30年以前」という「30」という数字を多数見つけていました。
しかし、あれから約6年が経過。
その間には、インタビューを受けた方が感じている「良き古着が見つけられない」ということが起こってきました。
もともと希少価値が高かった古い素敵なドレスなどをゲットできていたレベルの高さを持たれていたファッション通なる人なのです。
その方が、お手上げだと言われているということは、ファッションの先陣を切る方の正直な現実を見た感想なのです。
そうして、今後何が起こっていくのかというのは、「ヴィンテージ物」というますます希少価値が高まったアイテムの「ハイブランド化」だと見ています。
そうしますと、昭和時代の1980年代のお洋服全盛期のデザイナーブランド古着であっても、希少価値などまだまだだというようなレベルなのだということの裏返しのようなもの。
ただ、ヴィンテージの年数をルール付けするようなところまで本当にする必要があるのでしょうか。
そのように縛り付けて本来の装いの自由スタイルを奪い、かえって本当にその品物の良さを逃すと思うのです。
「ヴィンテージ」という観念に囚われて、「プライド」「ステイタス」でお洋服を選ぶような方向へ行きかねないのではないかと考えます。
本来お洋服を纏うことは自由であり、「表現」である以上このワードを使いたいこともあると思うのです。
その時にルール付けされた「ヴィンテージ」という言葉に対して躊躇してしまうことに繋がってしまうと予想します。
あとがき
ただ、「50年以上前ではないとヴィンテージとは呼ばない」というご意見にも頷けるところがありました。
よって、こうして自らの考え方も語る上では、まず「ヴィンテージ」というこれまでの使い方を別のワードに換える「手直し」をしています。
おそらく、今後ピクチャレスクのブログからは「ヴィンテージ」という言葉はこの記事以外には消えていきます。
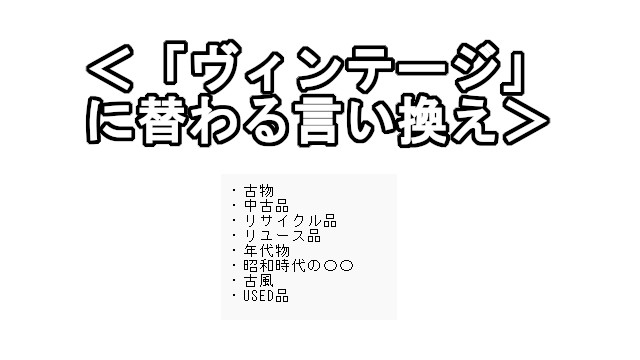
「もともと定義が曖昧なら、それぞれの着る人の価値観でヴィンテージと謳えばよいのではないか。。」これがピクチャレスクの考えです。
「こうあるべきだ」などとルール付けしたり縛り付けたりせずに、自由に一人一人に表現させてあげようではありませんか。
もっとお品物そのものの良さをちゃんと平等に1点1点見るべきであり、ただの「観念」だけではお洋服は成り立たないと思うからです。
人間の身体のラインを美しく表現するものが、もともと衣服ではなかったか。。そう思い直すと言い方など「ヴィンテージ」である必要などないのです。