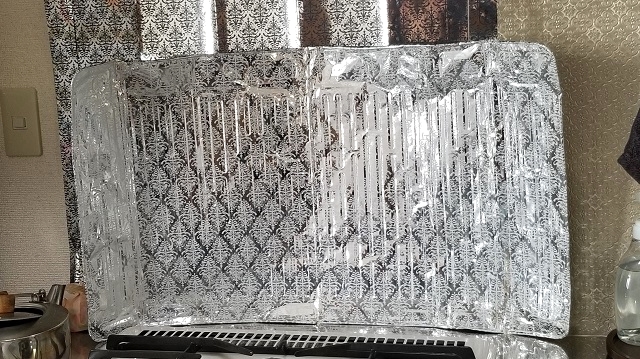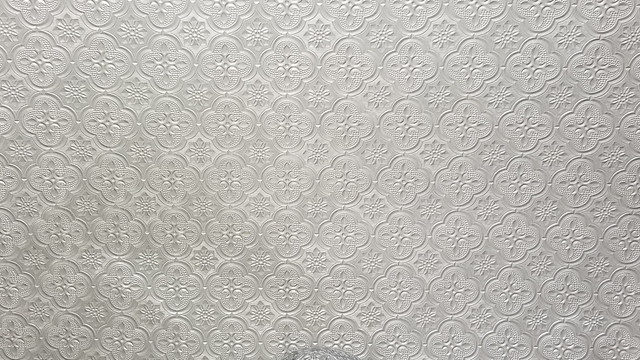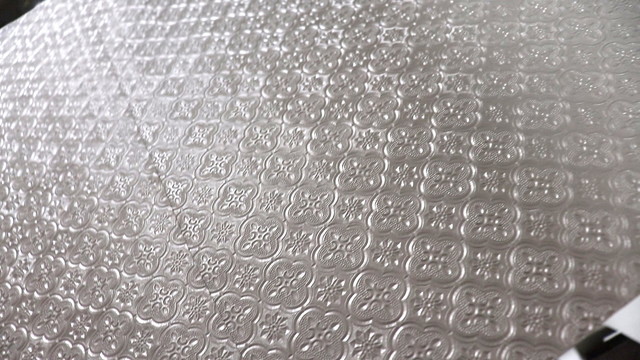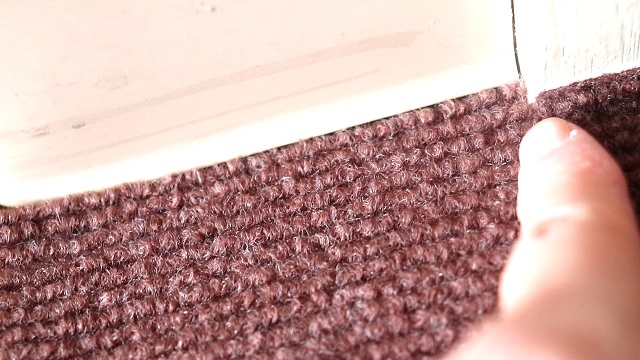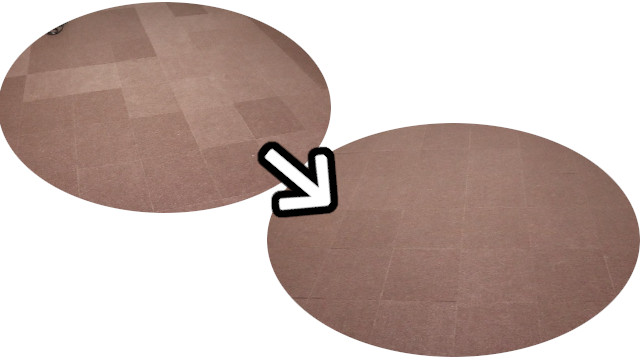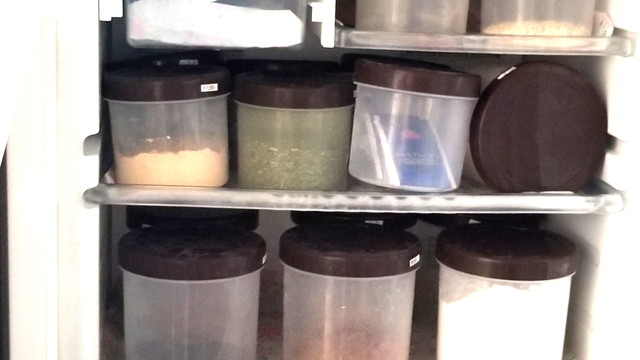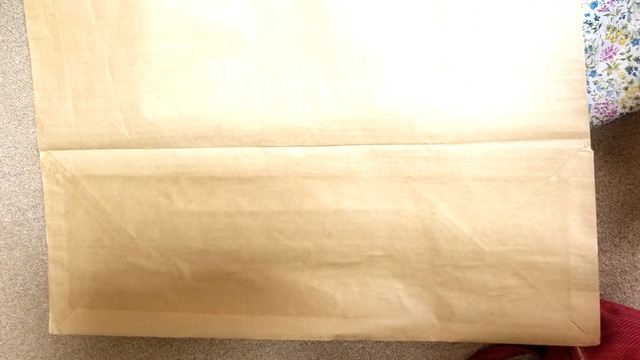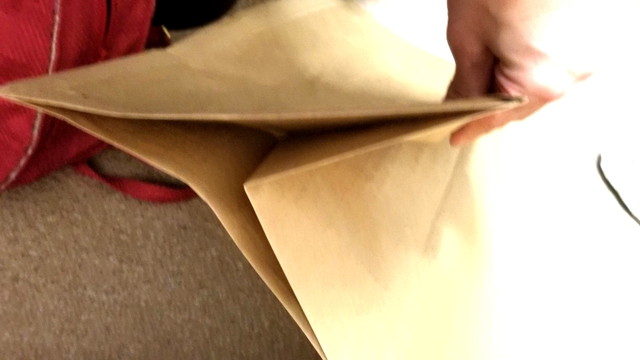まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
今回の記事はカテゴリーに悩むところですが、引っ越しを<コーデ>へ入れたので、「暮らし」の1つの話題として、<コーデ>のカテゴリーで投稿させていただきます。
2022年2月の頭に引っ越しをしまして、<引越シリーズ>として、引っ越し時に共有していただけるかもしれないと工夫や学びを①-⑭のシリーズで記事をアップしました。
インテリアに関するネタも満載♪、よろしければ、お立ち寄りくださいませ。
このたびは、引っ越しで一段落した1か月後でありながら、まだやり忘れていたことが分かったことがあります。
よく言われる引っ越し時の基本的なタスクの仲間に入れるべきだと思う事柄をご紹介したいと思います。
実際にうっかり忘れていたという事実から、もしかしたら見落とされてしまうこともあり、非常に重要な事柄でしたのでこうして記録に綴らせていただきたいと思います。
引っ越しの際によく言われているやっておくべきタスク、抜け落ちていた2つの事項も重要な自己責任項目
まず、基本的な引っ越し時に誰もがやるべきことという、ネット情報などでも多く書かれていたり、旧居の賃貸業者様からの資料に載せていただいていたりした事項を振り返ってみます。
・【転居届】・・・郵便局様に転居する日が決まり次第、おおよそで、新居のポストに入れることを開始する日を申し入れます。
その後旧居に郵便物が届いても、最大1年間くらいは新居へ転送していただけます。
・【免許証の住所変更】・・・警察様へは出向きますが、署内ではとても簡単にやっていただけます。
免許証の裏面に新しい住所が記載され、次の免許更新時には表に載り、裏面が空白になるといった流れ。
・【古物商の変更届】・・・「古物商」の免許がありますので、同じ警察様の部署違いで免許証と同日にお世話になりました。
こちらは免許証よりもやや時間がかかりますし、「住民票」が必要。
・【wifiの接続解除と新居でのwifiの申し込み】・・・旧居はオーナー様がご負担くださったものでしたが、新居では自主払いに変わったところが大きな変化。
そのまま同じ業者様が話がまとまりやすいと、個人払いに切り替えながら同じ業者様で継続。たまたま初期接続費用無料キャンペーン中であり、嬉しい偶然でした。
・【電気・ガス・水道の中止と新居での開始手続き】・・・これも少し失敗がありまして、お電話口の方に申し伝え方を、「旧居での停止と新居での開始との両方です」と言わないといけません。
たとえ、新居の住所などをお伝えしたからと言って、手続きは開始だけしかされていなかったということが実際にありました。
もっと気を使ってほしかったというのが本音ですが、いかに自己責任なのかという厳しさを感じます。
よって、無駄が無いように一度の電話の会話の中で、中止と開始とを両方共はっきりとした言葉でもってお伝えするというところが非常に大切。
水道に関しては、旧居は家賃の附随費用に含まれていたので水道代としては発生していなかったのですが、新居では水道代は別という違いがあり、うっかり申し込みを忘れていてあわててぎりぎりで申し込みをしたという実体験をしました。
これも気を付けたい点です。
・【銀行やネットの登録サイトなどの住所変更】・・・これがこのたび忘れていたことになります。
銀行のネットバンキングのアカウントも忘れがちですが、ちゃんとやる必要があります。
その他通販サイトは、非常に多くのネットサイトに登録してありましたので、変更を兼ね、今後も使っていくサイトのみに順次変更していきました。
半分以上がもう利用していないサイトだったり、何とサイト自体が廃業していたこともありました。この機会に「会員登録の解除」も検討し、デジタルの整理整頓ということをお勧めします。
登録情報と配送先が分離していることが便利なのでだいたいそうなっています。
両方共見直す必要がありますので、アカウントだけではなく、「配送先」も直すようにすることが大切です。
実際に、アカウントだけしか変更せず、配送先を前の住所のまま気づかず進めてしまい、たまたま近隣の引っ越しだったので何とかなったのですが、遠方の場合は大変です、お気をつけくださいませ。
現在は使用していない銀行様や保険会社様の住所を変更していないことも注意です。
これを放っておくと次の年末少し前の保険会社様からの控除証明書が前の家に送られてくるでしょう。
話の行き違いや紛失の原因になりますので、大切な健康保険等の加入中の住所の見直しなどは忘れがちながらとても大切なのです。
実は、こちらも実際に生命保険の会社様へ住所変更を届け出ていないことが分かりまして後からやった1つでした。
あとがき
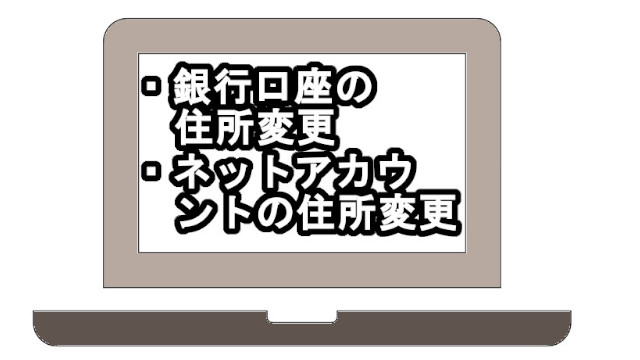
なかなか完璧にはできないものの、1か月経過して結構落ち着いてきた今だからこそ、改めて見直してみる必要があるのです。
引っ越ししたその年の終わりまでくらいは、年度の書類にかかわりますので、油断することなく手続きを早めに完了しておくことをお勧めしたいです。
「住所」はネット時代にはあまり身近な情報に感じなくなってしまうものですが、「何者なのか」を表す1つの証明として非常に大切なことであり、軽く見てはいけないということです。