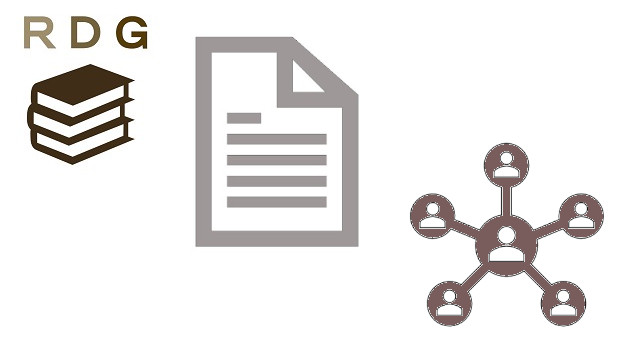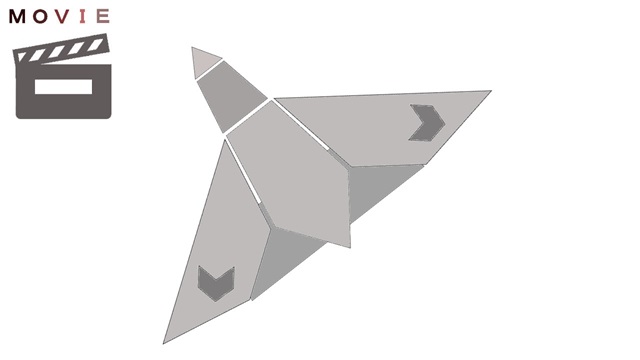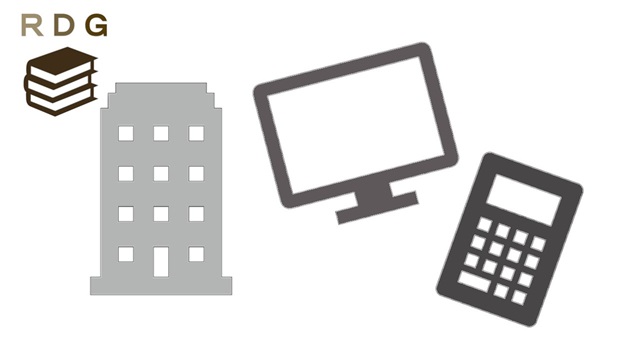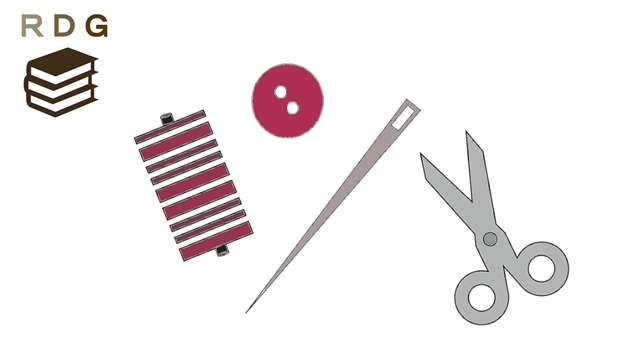まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
「本物志向のレンタルジュエリー」の事業者です。
ジュエリーを扱う立場としまして、宝石のことをしっかりと知るために、時々宝石にまつわる本を読ませていただくことがあります。
このたび1冊の本を拝読、「宝石物語:岩田裕子 著」です。
かつて貴族の宝飾品であった宝石にまつわる事実を中心に、やや盛られて言い伝えられた部分も含むストーリーを興味深く読ませていただきました。
フィクション的な部分もありながら、実在の歴史上の人物ばかりのストーリーであり、逸話としてジュエリーが様々な人間の人生に伴ってきたという見方では十分リアルです。
いつまでも永久に持ち続けることができる品物だからこそ、振り返った時のその存在感や過去の出来事の真実を知る唯一の手掛かりなるものであったとも言えるのです。
宝石のパワー、この世を作る地球を含む宇宙からの戒めや教訓を伝えるほどのものなのではないか

物語としては、宝石のパワーが人の人生を狂わせたような「ホープのダイヤモンド」のストーリーが有名です。
ここまで複数の持ち主を転々とした宝石はなかなかない、多くの所有者があり、どの持ち主も不幸の末路を迎えているようなのです。
特にパワーの強いカラット数の高いダイヤモンドだからこそのストーリーでありますが、宝石自体よりもむしろ、その宝石の価値に翻弄され、心が揺さぶられた人間の愚かな姿であるとも言えます。
現在は博物館という望ましい場所で佇んでいるようです、誰の手にも渡らない状態に行き着いたのでしょう。
キラキラ美しい宝石を前にしてどこか心が動揺し、揺さぶられるのも、そのあまりの美しさゆえ仕方がないのかもしれません。
しかし、こうも思うのです。
そういった煌びやかなお品を前にした時にこそ、優雅に落ち着いた気持ちでゆったりと接することが望ましいと思いました。
決して貪欲にならず周りに翻弄され過ぎない自分の軸を大切にしなければ不幸が起こるといような戒めを過去の宝石のストーリーから学んだわけですから。
急いで慌てて身に着けるのではない、ゆっくりと時間を使いながら、気持ちを落ち着かせた身に着ける瞬間をむかえたいものです。
例えば、収納1つにしても、ゆったりと宝石が喜んでリラックスするような収納の仕方というのもあるもので、宝石が喜ぶような向き合い方というものがあるのではないかと思っています。
せっかく価値ある綺麗さを放ってくれているのですから、私達はそのお返しとして、丁寧に、穏やかに接してあげることが大切ではないかと。。
あとがき
奇跡的に掘り出された地金と美しいストーン、決して当たり前ではないことが重なった宝石だからこそ希少価値が高いのです。
そして、研磨という透明感ある美しい磨きをかけてくれた宝石製造者様である人間の叡智にもありがとうの気持ちを持ちたいものです。
決して自分が発見できるものでもなく、多くの人の力がないと美しいお品を目にすることさえできなかったわけですから。
貪欲になるあまり忘れがちなこと、それは決して当たり前ではなかった奇跡があっての今現在への「感謝」の気持ちです(^-^)。