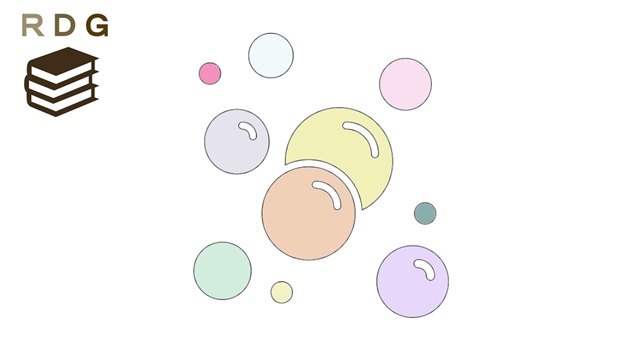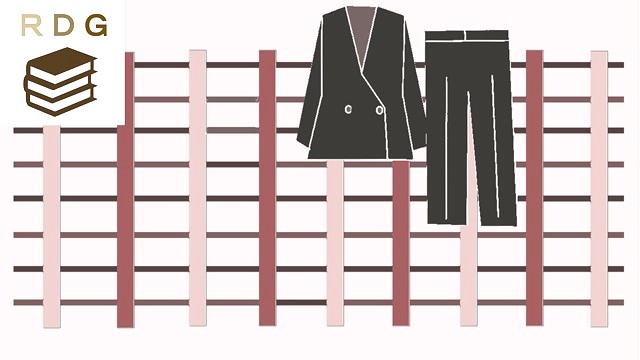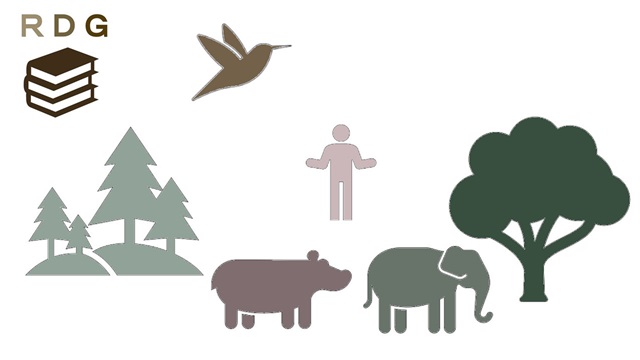まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
このたび、ルーティーン化した読書のたびに、こうして感想や思うところを投稿しています。
この内容の投稿は、カテゴリーの<読書>として集まっています。
このたびは、同時に2冊をご紹介。
2著書に共通するところが、著者様がWEB発信をされている方であるというところです。
「ユダヤ人大富豪の教え:本田健 著」と 「一生使える言い換え言葉:えらせん 著」です。
2著ともとても素敵なお話でしたが、共通するところが、物の見方や考え方の違い1つで大きく人生すら変わることです。
そう考えますと、著者様をネットで見つけたこと、そしてこれらの本との出会いは大変重要だったと思います。
「ユダヤ人大富豪の教え:本田健 著」:不思議な世界に案内されたような感覚、非常に素敵なストーリーにまとめられていた
非常に多くの書籍を発行されている「作家」様です。
最初は、YouTubeで知った方でしたが、作家様であるとを知り、著者様の中で一番有名な本とのこの本を読ませていただこうと思ったわけです。
とにかく、最初はYouTubeを拝聴したことがきっかけです。
非常に和やかなオーラみたいなものを感じるお顔やお話の様子と、通常胡散臭さを感じがちな「お金」にまつわる内容との良きバランスとがとても自然です。
ビジネスに通じる商業のやり方の根本の部分を著者様の実体験からストーリー仕立てで綴られています。
すごく素敵なお話で、しばらく余韻が残る程の内容。
1つの事象を見る時に、切り口は1つではない、固定観念こそがやっかいなもので、誰も見つけることの無かった点から展開して行けることのヒントをもらったような気がしました。
「一生使える言い換え言葉:えらせん 著」:知らない人にさえも愛情を持った人間でいられますように。。
おそらくYouTuber様でもあるのでしょうが、どちらかと言うと、頻繁にネットニュース記事でお見掛けする人物でした。
ここ最近、頻繁に記事が更新されていたことを見て、気になっていたところだったのです、
主に人間関係のノウハウといったようなことで、その中からとても印象に残ったことがありました。
「人間の悪い面よりも人間の良い面に注視した見方」です。
粗を探しがちな見方だとなかなか難しいことなのですが、この良い面を重視できると、おそらく、自分が大きく変わると思うのです。
このことの意味は、同じ人間をフラットに、そして愛情を持って見つめる姿勢だと思いました。
その姿は「心が広い人間」ということになると思います。
あとがき

事に対して人に対しての見方や接し方を能動的に自ら変えていくことで、随分景色が変わってくるということがとても素晴らしいことだと教えていただきました。
こういったことは、固定観念さえ取っ払うことができれば、何か特別な活動をするということではないものだと思うのです。
ただ、この固定観念が取っ払えないことが大きな課題であり、世の中の多くが人の悪い面を重要視する見方に偏っているのだと思います。
それは窮屈なところにいる不満や苛立ちのはけ口のようにもなっているかと。
まずは、「縛られた環境」から「自由」を入手するベースを持って、こうした考え方を受け入れていけるのではないかと自分なりに考えてみました(^-^)。