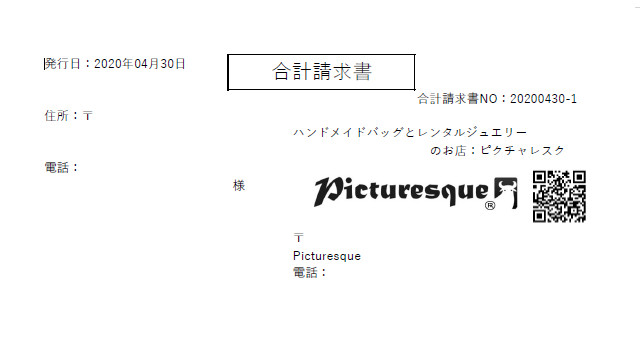まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
「個人事業主」になって4年目、2017年末に会社員を引退(「早期定年退職」と自分でからかっていますw)の2018年2月スタートでした。
店舗は事務所として使用させていただくのみの、ネット通販の事業の2つ、「ハンドメイドバッグ」と「レンタルジュエリー」の事業者でございます。
いずれも「ホームページ」や「販売サイト」を通じての商品のご提供となりますので、常に写真はご覧いただける状況にあるとともに、連絡のやりとりも当然、常に「営業中」なのです。
これは、考えてみたら当然の流れで、あえて「休業日」というものは設けておりません。
その年中無休に対する決意が生まれた理由をこのたびはお伝えしてまいります。
ショッピングする時にがっかりした経験を「反面教師」に活かした
ショッピングの時に、質問をしたいことがよく出てきます。
その場で解決したいご質問があっても、金曜日の夜以降はネットのお店が実質お休みになってしまい、月曜日にやっと連絡が付くなどということが結構な数ありました。
そうすると、金曜日からは3日後にもなってしまいます。
この3日は大きく、随分「時」の流れが変わってしまい、気分が萎えがっかりすることがありました。
質問というのは早めに解決したいものなので、やはりそういったお店の休業のロスが「ホットな気持ち」というショッピングでとても大事にしている者が気を落とす点だったのです。
そういった多くのショッピングの苦い経験を活かしたのでした。
年中無休のライフスタイルに慣れた今の楽しさ、すべての生活から事業へ取り入れる学びの多さ

「オン、オフ」という言葉もあるので、お休みの日にまとめてリフレッシュというのも会社員時代に長年経験しました。
普段会社で仕事にのめり込み(on)、夜遅めの帰宅、休日によくお昼寝を楽しんでもいました(off)。
仕事好きであるのは今でも何ら変わりません。
会社員時代のお仕事もとても好きでしたが、内容の変わった現在もその点が変わらなかったのが、「仕事内容への魅力だけが理由ではない」ということになりませんでしょうか。
「個人事業主」になるにあたっては、「自分の決めた仕事で、ずーっとお婆さん(今もそこそこお婆さん)になっても毎日毎日仕事に打ち込む決意を固めておりますので、このスタイルの毎日は当然で自然です。
ただ、「頭痛持ち」であることもあり、時々そんな時には数時間睡眠したり、ある一定の時間帯に毎日運動をする時間はいただいています。
あとは、店舗での材料購入などがある時の隙間のような時間に、電車の中10-20分の間で読書をするように本を持ち歩いて出かけます。
そんな感じで短い時間のリフレッシュを時折取り入れるようになりました。
現在観たい映画がある、感想や記録を<読書>カテゴリーでYouTubeとブログ記事にまとめるルーティーンの継続
映画なども、よく以前は夜の最終で見に行っていたこともありましたが、夜はYouTubeアップ作業があるので、現在はあまり向いていない時間帯。
途中のもっと明るい時間帯にリフレッシュとして取り込むのが結果グッドです。
現在見たい映画がありまして、「グリード ファストファッション帝国の真実」です。
「ファストファッション」への警告のようなメッセージを含むストーリーで、新聞の記事の「文化」のコーナーで「ファッションライター」様からのご紹介がありました。
もう間もなく上映スタート日になるので、時間が取れ次第、変な時間帯に見てみようと思います。
この変な時間帯というのが、午前中とか午後の夕方になる前の明るい時間帯。
現在サスティナビリティの内容の本を読んでいることもあって興味を持った映画です。
実は、映画も2018年以降映画館では見ていないと記憶しています。
感想などをまた、当ブログ記事にアップしたいと思います。
あとがき
「年中無休」の中で、時間のもったいなさを意識するようになったことが成果として1つあります。
しかしながら、何がもったいないかなど、何気なくやっていることの中にも今後につながるようなヒントがあるかもしれないので、一概には言えない部分。
よく、「徒歩なら迷うことなくタクシーを使う」など、そのような例を耳にしますが、徒歩でも意味がある場合もあるので、時間の使い方の極論だと思います。
後から考えて無駄だったなあと自分で思わなければ、徒歩で時間をかけたとしてもOKなのではないでしょうか。
「こういうものだ」と教科書のように従うよりも、「心からの納得」に重きを置いた方が良いです。
よって、みんなが横一列ということは決してなく、「価値観」というものの違いが千差万別で良く、この度の内容も年中無休に対する向き合い方の1つの例です。
とにかく自分の人生は誰かに占領されるものではなく、自分が舵を握れる「自由」がまずベースにあると思っております。
その「自由」が無い状況は誰かに奪われた人生であるので非常にまずい、早急に見直し解決する必要があると思います。
まずは「自由」を入手してくださいまして、「自分軸」の実現をしてくださいませ、心より応援致します(^-^)。