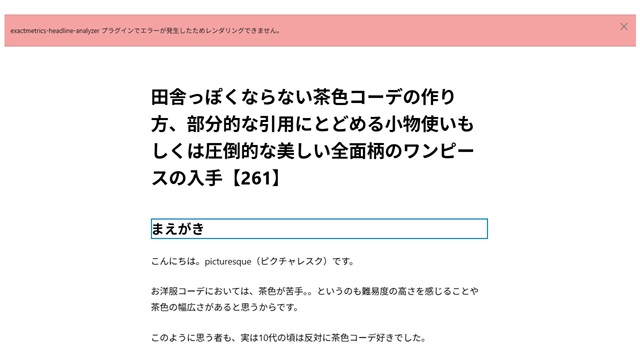まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
2025年は本当に多くの事が動く年なのかもしれません、いよいよネット検索エンジン内に、「AIモード」が設置されました。
これまでの検索結果は「Google」様では「すべて」と表現された左から2番目です。
「AIモード」の検索結果を2事業名「共有型のハンドメイドバッグ」「本物志向のレンタルジュエリー」両方で確認してみたところ、誤解釈が見つかったのです。
「まだ試験的な期間であり、誤表示もある」との断り書きもありましたが、この期間こそ多くの人に誤解を招いてしまう注視するべき時期だと懸念、早速修正を申し出たのです。
ネット検索の「AIモード」の結果の誤表示・誤解を指摘、同時に自社ホームーページ内の説明の曖昧さも見直した
「AIモード」の検索結果による説明に誤解があることに気付いたのも、そのつもりはなかった確認作業が結果的にはエゴサーチになっていたからこそ。
実のところ2事業共誤表示の部分があり、フィードバックボタン(検索結果の右端の縦に並ぶ3つの点の中にある)を押して、誤表示の指摘ができる仕組みになっていたのでそれを利用。
では、誤表示と事業者本人が感じ、修正依頼した内容の部分を解説します↓。
「共有型のハンドメイドバッグ」の誤解釈
「共有型」という言葉は、辞書には載っていません。
私が勝手に付けた呼び名であり、「共有スタイルの」に等しい意味です。
その「共有」という言葉の捉え方が「AIモード」では薄く掬い足りないという感想でした。
「家族や夫婦間やパートナー同士でバッグを共通に使う」というような解釈が中心に表記されていました。
ところが、これまでどのブログ記事にも販売サイトの「creema」様にもこうしたことを記載した記憶が無いのです。
「メンズライク」というような表現を多く使ってきたことで、「ユニセックス」「老若男女」という意味をこめて表現されたのかもしれません。
事業者本人の「共有型」は全く違う解釈でありまして、2つの立場の「共有」を謳っています↓。
1つは、同じようにハンドメイドバッグを作る製造者様との共有。
確かにピクチャレスクが考案したデザインやノウハウのバッグであっても、それをみんなで共有して使えるものにするということ。
そこに「著作権フリー」も伴うのです。
そして、ぱっと見で全部同じモデルであっても部分的な引用でもどちらもOK、了解など得ずに勝手に製造し商業利用の販売やSNS投稿もOKというスタイル。
ただし、「商標権」などの取得は不可、独占は誰もできない「共有型」なのだという意味なのです。
これは、世の中では滅多にされていないスタイル、理解されることが難しいのかもしれません。
そしてもう1つ、購入して下さったバッグのユーザー様との共有。
ご購入後、何年か経過後の「気持ちの変化」「部分的傷み」などの解決のために、バッグを解体して別のものに仕立て直す「リメイク」もOKなのです。
更に、そのリメイク品も販売などして商業利用がOK。
これも立派な1つの「共有」の形。
こうして、事業活動の目的、「ハンドメイド文化を世に広める」ということの実現に向かうのです。
「ハンドメイド」と「リメイク」は本来相性の良いものなのに、「著作権行使」がその行く手を阻むのです。
この現実と向き合い、可能なことをしていくというスタイルなのです。
どうでしょう、「バッグをみんなで使う」という表示は、相当な誤解釈ですよね。
「本物志向のレンタルジュエリー」の浅読みの懸念
「本物」というのは、18金やプラチナなどの本格的な貴金属とダイヤモンドなどの研磨された美しい希少な宝石とのコンビ。
この解釈は正しいです。
ただ問題は、「志向」をどこまでご理解いただいているのかということです。
「本物志向」と謳い実際のラインナップが、誰もが頷ける美しさと本格派の隅から隅までの勢揃いだからこそこの言葉の価値が高まるのです。
「志向」の意味は、今後も変わらず本物を目指し続ける右肩上がりの姿勢のこと。
決して本物に似せた「模倣品ダイヤモンド」などの「本物に極めてそっくり」という本物との区別の意味ではないのです。
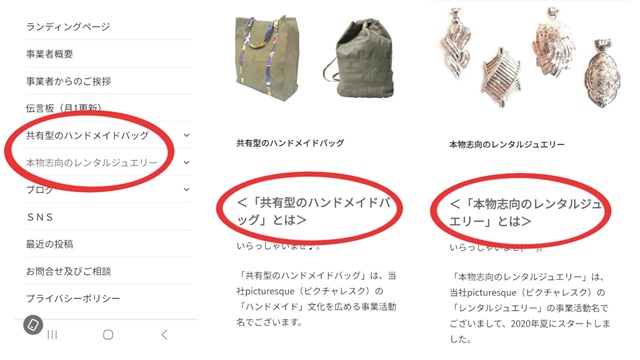
あとがき

第3者が正しく他者を説明することの難しさがまだ残ります。
この先のより良きAIの発展があることを望みます。
いつか事業活動の目的を理解され受け入れられると良いと願っております。
裏に邪(よこしま)な姿勢がある事業はなかなか難しい時代になるのではないかと期待します。
それが本当の道理であり、「正直者がバカを見る」「白を黒と言いくるめる」がまかり通ってきた時代からの発展であると考えます(^-^)。