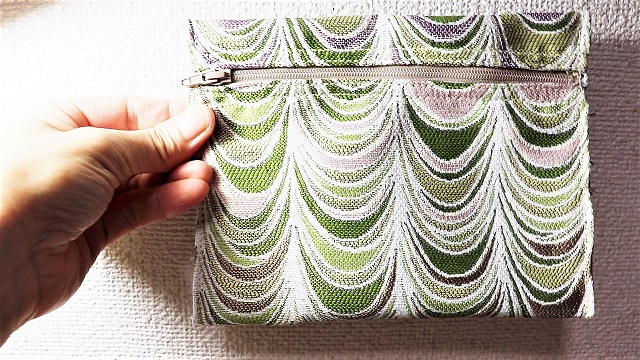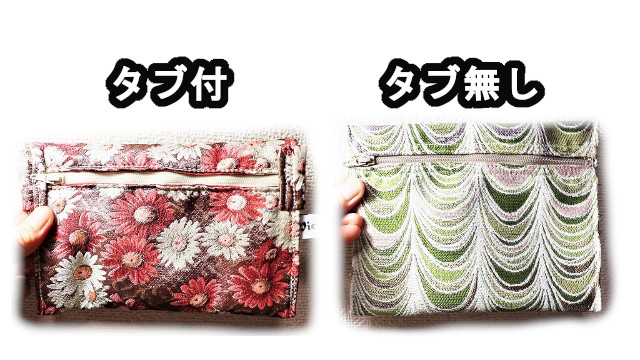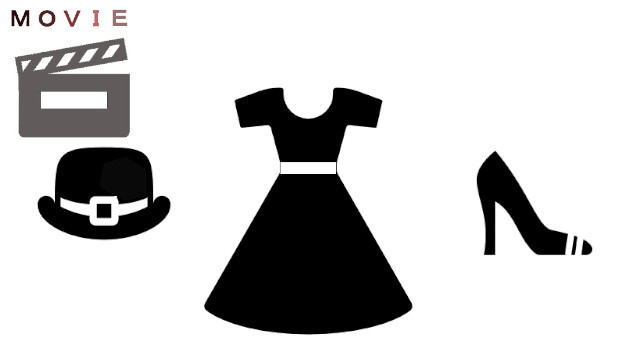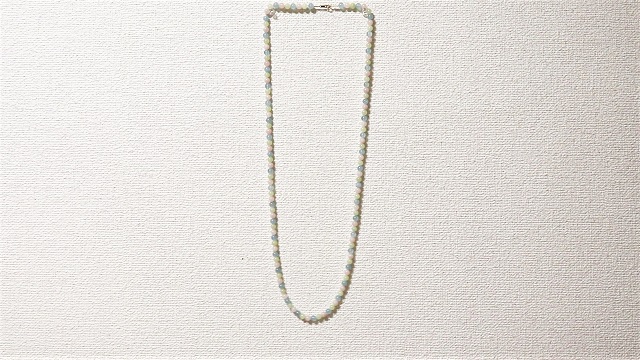まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
ファッション関係の映画を積極的に観るようになりました。
他の分野の映画も、もちろんそこからのヒントが斬新だったりすることもあるかもしれませんが、ファッション関係のあるお仕事をさせていただいている以上見ない手はありません。
今回「ココ・シャネル 時代と闘った女」を鑑賞。
1時間足らずの映画であり、ショートの部類です。
見た後の何かずっしりとした重み、この重い気持ちこそがこの映画から感じたことでした。
自分の生い立ちなどを語りたがらなかった主人公の代りに映画が語ってくれたこと
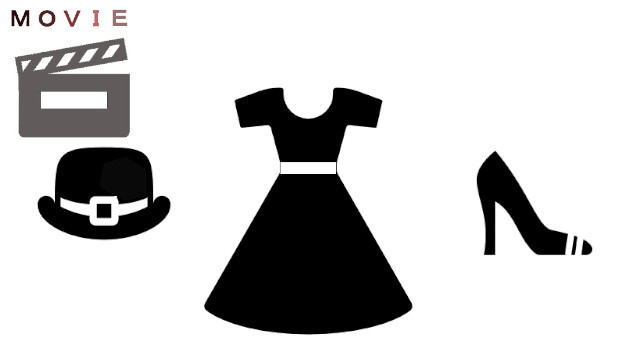
「ガブリエル・シャネル(通称「ココ・シャネル」)は、その眩いまでの成功によりたくさんのスポットライトを浴びてきたかと思います。
しかし、この映画はむしろ、そのウラハラの、知られていないような部分に注目していると言えます。
これまで随分多く映画の題材にもなってきた「シャネル」様でありますが、このたびの映画化の意図が「みんなが知らないシャネル」というような部分を伝えたかった点にあったのかもしれません。
家庭環境に恵まれなかった辛く厳しい幼少時代のバネの跳ね返りが人生すべてというほどのものだった
よく、「苦労した過去をバネに。。」などと言われますが、まさにそういう一人が「ガブリエル・シャネル」様だと思います。
幼少期に親に見放され、修道院生活をしてきた孤児。
その辛い辛い体験から始まり、疑問だらけの満たされない日々を自らの強い決断をいくつか突破しながら脱出していき、成功への長い階段を迅速に駆け上ります。
決して、育ちの良い気品あふれた。。などという雰囲気ではない、どちらかというとやさぐれたようなタイプ(と思ってしまいました汗)、嫉妬深くて決して言葉使いが綺麗とは言えません。
先見の明ともいうべき、ここぞという分岐点を自分で感じ取り判断し、大きく舵を切っていくという手腕はこれまでスポットライトを浴びてきた部分で多くの人々から評価されています。
この映画が1時間もない短いものであるのも、「ガブリエル・シャネル」様がいかに人生を精一杯全力で駆け抜けたのかという疾走感がより伝わるよう。
完全ドキュメンタリーではない部分が多いですが、本人がマスコミにインタビューなどで語る姿はリアルです。
どちらかというと気ぜわしく、せかせかしたイメージのお話のし方なのです。
途中に大きな戦争があったり、亡命などもあったりで、そんな事情からか、故郷フランスではなくスイスにお墓があるようです。
あの納得していないような表情は何なのかを自分なりに解いてみた
本当のことは本人しか分からないものですし、特に幼少の頃のことは隠し通していたとのこと。
隠して語りたがらなかったところに答えがあるような気がしています。
その映画の中に出てくるご本人の表情が決して幸せに満ち溢れた笑顔では決してないことがとても引っ掛かりました。
あれだけの成功をおさめていながらもなぜあのような表情をしているのだろう。
功績とのあまりのギャップに疑問は、ますます高まります。
「たった一人で時間をかけて下から這い上がっていくタイプ」なのか「他の人の力を借りながら迅速に登っていくタイプ」なのか。。いずれも同じ成功という結果です。
「手相占い」にも運命線がどの位置にあるのかで、その両者が分かれるとのことがよく語られます。
どちらでも同じゴールなら良いですし、力を借りた人に感謝して「ありがとう、おかげ様で。。」という言葉や気持ちがあればたどる運命が違った道順だっただけ。
運命を切り開いたのは良き人物との出会いや素晴らしい直感などです。
幼少の頃の疑問、「なぜ親は自分を捨てたのだろう」という解決ができないまま、その子供の時の強い疑問を持ったまま大人になっていってしまったという点が非常に悲しく、心の奥の未解決部分だったかと。
そのことを忘れるかのようにがむしゃらにお仕事されていったのかもしれません。
現在も存続の一大ブランドを作った人の本当の気持ちという視点で少しだけのぞいてみました。
名前だけの一人歩きもある現在では、その華々しい功績が語られることだけが多いですが、その生い立ちがバネになった結果であると考えると、「闇」の部分「心の奥底」の部分も成功と同じくらいの対極にある真っ暗闇なのだと。
そういった意味で、この映画は重要なスポットにご注目されたのではないかと思います。
あとがき
「シャネル」ブランドは、特にアメリカでは大きく支持された点も誇らしき功績。
他の皇室ご用達の伝統ブランド、貴族財であったアイテムを作ってこられた数々の「ハイブランド」様との違いが「シャネル」様にはあるのでした。
最初から良い位置付けに恵まれたブランド様とは違って、無名時代があり、底から登って行き、現在に至ってもそれらの伝統ある御用達ブランド様の数々と肩を並べている存在感の維持が素晴らしいところ。
当の本人が語りたがらなかった隠し通した幼少期の不遇時代。
現在のここまでのファンの多さとブランドの継続をどこかで見守り、どうぞ「微笑み」を浮かべてくださればと思います(^-^)。