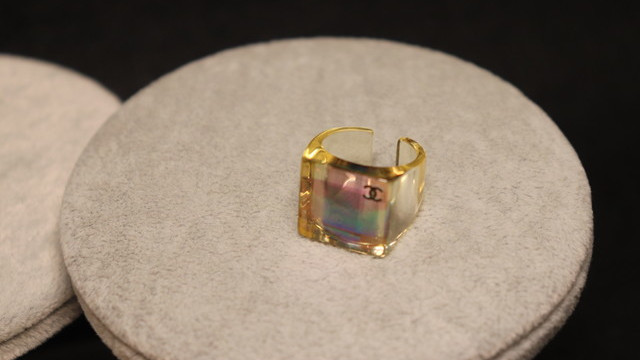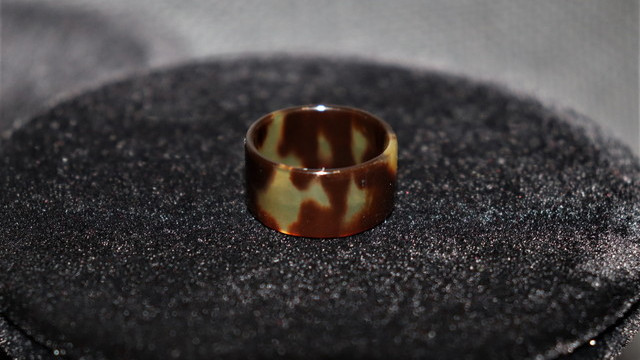まえがき
こんにちは。picturesque(ピクチャレスク)です。
「トルコ」という国のエキゾチックなイメージ。。「ベリーダンス」という舞踊もレストランやバーで演じられる光景を動画で拝聴したことがあります。
ぼんぼりと房のコンビがトルコらしさをたっぷり感じる925製のペンダント、受け取った瞬間余りの美しさにうっとりとしたを覚えています。
エキゾチックな雰囲気を高める更なる他のジュエリーとを組み合わせ、お洋服とも合わせていきました。
美しい細工のペンダントは一層高まった、925ジュエリーの段差重ね付けでカーネリアンが明るく全体を照らしてくれたからだ
2015年当時で¥12,000くらいだったかと。。ペンダントトップのみの価格のシルバー925製のトルコ製の房ペンダント。
様々な房ペンダントの見比べによる厳選で、ダイナミックさも一番だと感じたこのペンダントトップからコーデが始まりました。


カーネリアンペンダントは、しずく型の多面カットがされたエレガントな細工。
長い方のタッセルペンダントと良き相性、段差重ね付けの上下が違和感なく繋がります。



コットン素材であるワンピースは気さくなSV925ジュエリーとの相性があります。
シフォンやサテンの衣装的なワンピースが18金やプラチナに合うことに対しては、活動的なシーンの着用が見込めます。
とは言え、エレガントVSカジュアルという違いを超えたものをここに感じます。
わずかに聞こえる自然の営みが、優しく響き渡るかのような神秘的で静寂な場面がそこに1つの世界観として現れたのです。
あとがき
当ブログ記事は、当「本物志向のレンタルジュエリー」の内容を高め過去の廃番となったセットも装いのご提案をするラインナップの記録です。
当時、サイズなどの内容説明のみであったこのお部屋をブログ形式に改良、順番に綴り直しをしておりましてこの番号<旧53>は、2025.12.28に行っています。
<旧>という番号は、2020年の開始当初1年くらいのラインナップ、集めていた個人的な時代の要素がまだ残る点がかえって日常的なジュエリーコーデの例になれるのではないかと。
シーン別にジュエリーを使い分けるということは、実のところ日本人の特性でもあります。
真珠をきちんとしたシーン用の花珠(はなだま)と活動的なシーン用のイミテーション(偽物)とで使い分けるような習性。
場面ごとの意識のようなものを繊細に知覚するような民族性、非常に奥行き深い特性は使い分けの文化を作った。。今後も大切にしていきたいですね(^-^)。